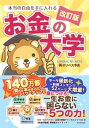プラチナNISAおよびこどもNISA復活については、2025~2026年度の税制改正で正式検討・決定される見込みです。これらが、いい面と良くない面がある。以下3点を取り上げてみました。
高齢者優遇・ジュニアNISA復活・毎月分配型投信の行方──NISA制度改正を読み解く
2025年現在、NISA(少額投資非課税制度)をめぐる制度改正が相次いで議論されています。その中でも注目を集めているのが「高齢者優遇のプラチナNISA構想」「ジュニアNISAの復活検討」「毎月分配型ファンドのNISA対象 inclusion(改悪懸念)」の3つです。本記事では、これらの制度改正が意味するもの、そしてその裏にある意図と問題点を深掘りしていきます。
1. 高齢者優遇「プラチナNISA」構想──優遇か、それとも資産の吐き出し政策か?
政府は65歳以上の高齢者を対象とした新しい非課税投資制度「プラチナNISA」を検討しています。現行NISAとは別枠で、年間100万円、最大500万円の非課税投資が可能となる構想です。さらに、これまでNISA対象外だった毎月分配型ファンドの利用も可能になる見込みです。
しかしこの政策、果たして誰のためのものでしょうか?
◆ 懸念点
- 長期運用と高齢者のライフステージのミスマッチ:高齢者は突発的な医療リスクや生活環境の変化に晒されやすく、10〜20年スパンの投資が現実的に機能しづらい。
- 実質は貯蓄の取り崩し誘導か?:日本の高齢者が保有する膨大な預貯金(総額1000兆円)を経済に流すための仕掛けとして、政策的な”資産の吐き出し”を誘導する可能性。
- 制度の逆進性:十分な金融資産を持つ高齢者にはメリットが大きいが、低所得層や慎重な層にとってはリスクを押し付けるだけの制度に。
“高齢者のため”を掲げながら、実際には市場に資金を流すための装置になっていないか。制度設計の目的をもう一度問い直す必要があります。
2. ジュニアNISA(子どもNISA)復活検討──金融教育の起点として期待される制度
2023年末で制度終了となったジュニアNISAですが、金融庁や一部政治家の間で「子どもNISA」としての復活案が浮上しています。これは、18歳未満の未成年者にも非課税投資の枠を提供し、家族単位で資産形成を進める制度です。
◆ 評価ポイント
- 家庭内での金融教育に効果大:親子で資産形成を学びながら、若いうちから”お金の使い方”を体験できる貴重な機会。
- 制度の除外理由が不明確:新NISAでは18歳未満が除外されているが、その明確な理由や根拠は示されておらず、再検討の余地は大いにある。
- 一時的なつなぎ運用もあり得る:制度が再開するまでの間、特定口座で1年程度運用を待つのは合理的な選択肢。
投資教育こそ、これからの時代に欠かせない教養。こどもNISAの復活は日本の金融リテラシー向上に直結する施策です。
3. 毎月分配型ファンドのNISA inclusion──“擬似配当”による制度の本質的改悪
プラチナNISAでは、これまで対象外だった毎月分配型ファンドを認める方針も検討されています。これに対して、多くの識者・投資家から「制度の趣旨と矛盾する」「改悪ではないか」との声が上がっています。
◆ 問題点
- 元本を切り崩す仕組み:多くの毎月分配型は実質的に運用益ではなく元本を払い戻しているにすぎず、資産を増やす投資とは言えない。
- 手数料ビジネスの温床:信託報酬が高く、販売会社の利益構造を温存。高齢者をターゲットにした“商品販売型金融”の悪習を助長。
- 誤解を生む制度構造:「毎月お金が入る=儲かっている」と誤解しがち。特に高齢者にとって、擬似的な安心感を与える罠となる可能性がある。
積立NISAや成長投資枠が目指す「長期・積立・分散」の理念と真逆。これは“制度を悪用した金融商品の売り場化”に他なりません。
終わりに:制度改革は「誰のため」かを常に問え
NISA制度の改革は、本来「誰もが資産形成できる社会」の実現を目指して始まったものです。にもかかわらず、
- プラチナNISAは実質的に高齢者の資産を市場に流す装置、
- 毎月分配型の inclusion は制度を歪める”利益誘導”、
- ジュニアNISAは本来あるべき教育の場を失っている、
という状況では、本末転倒です。
制度設計において、もっとも大切なのは「利用者の利益を中心に据えること」。今こそ、国民が声をあげ、制度が誰のためにあるのかを問い直すときではないでしょうか。
下記は自分のネット環境や情報の参考にしているものです。ご参考までに。