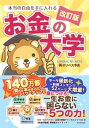先日テレビ番組で『夢と金』のエッセンスを実例交えて紹介していました。本書は“夢をかなえるにはお金の仕組みを知らねばならない”というメッセージが貫かれていますが、放送時間の制約上すべてを語り切れません。そこで今回は、3部構成のポイントをギュッと要約し、“投資初心者にもわかりやすい”ブログ形式でお届けします。
第1章:富裕層の生態系
1. 知識不足で命を落とすな
- 何が危ないか:お金の仕組みを知らないと、借金の罠や詐欺に引っかかったり、高すぎる手数料を何年も払わされたりします。
- 具体例:たとえば「借金を返せず破産→自己破産後の生活再建が難航→心身の不調」というパターン。投資初心者はまず、銀行預金・ローン・投資信託の違い、税金(譲渡益課税)や手数料の仕組みを押さえましょう。
2. 「高価格帯」にクレームを入れるバカ
- 価格ではなく“対価”を考える:同じ1万円の時計でも、ブランド品なら長持ちするメンテナンスサービスや再販価値があります。投資信託なら、成績優秀な運用チームのリサーチ力やサポート窓口が“お金の価値”です。
- ワンポイント:「安物買いの銭失い」を避けるために、コストだけでなく、得られる恩恵(安心感・専門家のフォローなど)も比較しましょう。
3. プレミアムとラグジュアリーの違いを知れ
- プレミアム(高品質)…「基本がしっかりしている」
- 例:経費率0.1%で安定的にベンチマークを上回るETF
- ラグジュアリー(贅沢)…「特別な体験や希少性」
- 例:限定版アートを扱うNFT、プライベートバンキング
- ポイント:自分が「安心」を買いたいのか「特別感」を買いたいのかを明確にし、それに合う商品を選ぶ。
4. 夢の計算式
- 「ゴール」と「資金計画」をつなげる
- ゴール金額を決める(例:5年後に300万円必要)
- 自力積立か運用リターンでまかなうか選ぶ
- 必要利回りや毎月積立額を計算する
- 使えるツール:ネットの「積立シミュレーター」や電卓アプリで、数字を入れるだけで具体的な道筋が見えます。
5. 機能を売るから「高い」と感じさせてしまう
- 機能説明だけでは心に響かない
- 例:年率5%と書かれたチラシを見るだけでは、なぜそれが自分の生活に必要か伝わらない。
- ストーリーを語る
- 「この商品を買えば、老後も安心して趣味に打ち込める」など、未来の自分の姿を想像させる言葉を添える。
6. 資金提供者の生活を想像しろ
- 相手の立場で考える:ベンチャー投資家なら「出口(売却益)戦略」を重視します。年金生活者なら「安定収入」を重視。
- 提案の作り方:「御社の●●事業は社会貢献性が高く、自分も応援したいので投資したい」という共感を呼ぶ資料を用意する。
番外編:脱・労働集約型/脱・完売思考
- 脱・労働集約型…自分の「時間」ではなく、「仕組み」で稼ぐ
- 例:自動積立投資、インデックスETF
- 脱・完売思考…「売り切り」ではなく「継続的な関係性」
- 例:会員制ファンド、運用報告会の開催で長期フォロー
第2章:コミュニティ
1. 「機能」がお金にならないことを受け止めろ
- 機能だけでは差別化できない:たとえば「〇〇銘柄に投資」という機能は他にも山ほどあります。
- 熱量と関係性がカギ:「この人の考え方が好きだから応援したい」という“惚れ”が、お金を動かします。
2. ハイスペックとオーバースペック
- ハイスペックOK/オーバースペックNG
- 必要十分な機能だけを持たせ、余計なコストを削減
- 歴史的大敗例:かつての高画質オーディオ機器が高機能を謳ったものの、高価格で普及せず市場から消えた
3. 【機能検索】から【人検索】へ
- 情報収集の変化:今は「○○ができる商品」よりも「□□さんの商品」が検索される
- SNS活用:運用担当者の顔が見える動画やブログで、顧客と双方向コミュニケーションを築く
4. 「正しいサービス」より「惚れるサービス」
- ロジックだけでなく感情に訴える
- 数字よりも「あなたの夢を実現したい」という言葉が刺さる
- 具体例:投資信託会社が顧客の成功体験インタビューを公開し、「自分もこうなりたい!」と思わせる演出
5. 相場を無視できる【人検索】の実例
- 熱狂的ファンの力:クリエイター支援型ETFやクラウドファンディングで、運用成績よりも理念に共感した人が資金を集めた例
6. 求められているのは「顧客のファン化」だ
- 単なる顧客 → ファン
- サポーター感覚で商品を継続購入
- 例:月額コミュニティサービス、限定セミナー
7. 「応援シロ」の計算式
- 応援量=(会費+寄付額)×継続期間×紹介人数
- 活用方法:初期目標を「会員数100人・継続期間6ヶ月」と置き、必要なマーケ施策を逆算する
8. 「ファン創造」の実例
- 成功事例:小規模ファンドが毎月配信する運用レポートにファンが感動し、自発的にSNSで拡散。新規顧客が増加。
9. コミュニケーションはどこから生まれるのか?
- 心を動かす瞬間:成果共有、サプライズプレゼント、感謝メッセージなど
- 仕組み作り:定期的なフォローアップメールや、顧客アンケートで双方向の関係性を築く
10. 不便がもたらす価値
- 不便は“体験”を生む
- 例:紙の会報誌限定配布→手に取る喜びと特別感
- 投資コミュニティ版:リアルオフ会を開催し、オンラインだけでは得られない絆を強化
番外編:お金のイロハ〜借金は悪いもの?
- レバレッジの正体:「借金コスト<投資リターン」であれば理にかなった手法
- リスク管理:返済プランと最悪シナリオをあらかじめ計算し、無理のない範囲で活用
第3章:NFT
1. 海に沈んでいるお金の話
- デジタル資産の多様性:NFTのほか、DAOトークンやゲーム内通貨など、まだ価値が認知されていない“沈み資産”が多数存在
2. 新しい扉の前にはいつも長い説明がある
- 学習コストの乗り越え方:まずは「トークンを買ってみる」「小額でミニNFTを発行してみる」といった実体験が理解を促進
3. NFTをメッチャ簡単に説明してみる
- 超かんたん定義:デジタルモノに「唯一無二の証明書」を貼り付ける技術
- 価値の源泉:「世界に1つしかない」という希少性と、持ち主の履歴がブロックチェーンに刻まれる信頼性
4. 絵本作家の新しい収入源
- 従来モデルの課題:印税収入は再販時に作者に入らない
- NFTモデル:「作品の所有権をNFT化し、二次販売時にも1~10%のロイヤリティが作者へ還元」
5. NFTというラグジュアリー商品
- デジタルの贅沢:限定エディション、作者のサイン入りデジタルファイル、高解像度版の提供
- コレクター心理:「他人が持っていないものを持ちたい」という所有欲を刺激
6. お金のような「共同幻想」
- 信認経済の本質:ドル紙幣もNFTも、「みんなが価値を認める」という合意の上に成り立つ
7. 「デジタルババ抜き」になるNFT
- 過熱相場の罠:急騰銘柄に飛びつくと、最後は転売できず値崩れリスク大
- 対策:プロジェクトの開発継続可能性や取引量、ホワイトペーパーをしっかり読む
8. AI×NFTで活動資金を作る
- ハイブリッドモデル:AI生成画像をNFT化+コミュニティ投票で次回作品を制作。売上を再投資して循環させる
9. 人を助けるためのお金を集めるツール
- 公益性の高いNFT:チャリティーオークションや、寄付先をチェーン上で可視化できる仕組み
10. 時代を正しく把握しろ
- 波を読む:NFT先進国の動向(米国・韓国)、国内規制の動き、メタバースとの連携などをウォッチし、自分の強みを活かせる領域を見定める
あとがき〜夢と金〜
この3部構成を通じて、一貫するのは「夢を現実にするには、まず“お金”を正しく理解し、活用できる自分自身を育てること」です。
初心者の方も、まずは小さな一歩(少額投資、無料セミナー参加、コミュニティ参加)から始めて、知識と経験を積み重ねていきましょう。応援しています!
下記は自分のネット環境や情報の参考にしているものです。ご参考までに。
created by Rinker
¥1,870
(2026/01/28 09:46:52時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥1,601
(2026/01/28 09:39:55時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥1,958
(2026/01/28 09:39:55時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥264,000
(2026/01/28 09:39:56時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥9,990
(2026/01/28 09:46:52時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥84,416
(2026/01/28 09:40:14時点 楽天市場調べ-詳細)
Visited 46 times, 1 visit(s) today